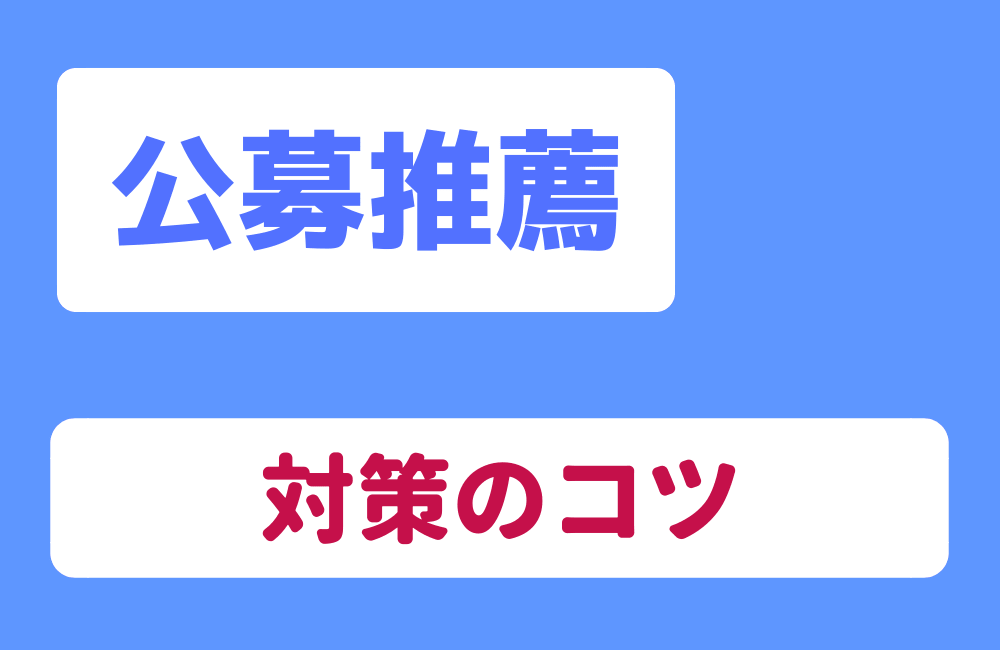公募推薦の基本や、具体的な勉強法について指導経験を活かしてまとめました。
指定校推薦のように高い確率で合格が約束されている推薦入試とは異なり、公募推薦は志願者数によってはかなりの狭き門となる入試です。
さらに、本気で合格を目指すのであれば面接対策や小論文対策が必要であり、一般的な受験勉強と並行してこれらの対策を進めると少なからず自分に負担がかかることも事実です。

とりあえず受けとこうかな。
なんて半端な覚悟では、推薦入試に落ちるどころか、一般入試の対策までおろそかになる可能性もあることを意識しておいてください。
それでは、これらのことを踏まえて、いったいどんな人が公募推薦に受かるのか、どんな対策をすれば有利になるのかなどについて解説していきます。
そもそも公募推薦とは?
推薦入試は大きく3つに分けることができます。

(1)指定校制推薦
指定校制推薦は、大学が特定の高校などを指定して行う入試方式のことです。
大学が高校側を全面的に信用し、推薦された学生は「ほぼ100%合格」します。
推薦にあたっては校内選考が実施され、その通過者が学校の代表として推薦されます。
主に、私立大学で行われます。
基本的に専願ですので、合格したら必ず入学しなければなりません。
(2)公募制特別推薦

スポーツや文化活動など、学習面だけではない部分が高く評価される入試方式です。
評定平均値の基準を設けている大学は多くありません。
ただし、県大会優勝や何らかの受賞経験などの高いハードルが課されているので、要項をしっかり確認して、「そもそも自分が出願要件をクリアしているのか」をチェックしなくてはなりません。

大学生オリンピック選手は特別推薦のイメージです。
(3)公募制一般推薦
各大学ごとに出願条件が示され、その条件を満たし、出身学校の校長から推薦された学生が受験可能な入試方式です。
国公立・私立を問わず多くの大学がこの公募制一般推薦入試を実施しており、評定平均値を出願基準としています。
また、ほぼ100%合格する指定校推薦とは異なり、必ず合格できるわけではありません。
そのため、出願書類の提出だけではなく、面接試験や小論文試験にも力を入れる必要があります。
ちなみに、基本的に専願ですので注意が必要です。(不合格だった場合は他の大学に出願できます)

チャンスを増やす意味で受けるといいですね。
受かりやすい人、受かりにくい人の比較ポイント
(1)調査書の内容
調査書は、推薦入試で最も重要な書類です。
平均評定、特別活動、生徒会・委員会活動など、高校在学中のあらゆることが書かれている、受験者の詳細プロフィールのようなものです。
平均評定が高く、特別活動や生徒会活動に熱心で学校側の評価が高い学生は、入試でも有利になりやすいです。
もし調査書の平均評定が低く、特別に記録する内容も無いのであれば、
- 本当に推薦入試を受けるのか
- どれほどの時間を推薦入試対策に割くか
について検討しましょう。
(2)面接の内容
公募推薦は、大きく分けて
● 面接重視型
● 書類選考・小論文重視型
に分かれます。
面接重視型の場合は、当日の面接によって合否が大きく左右されます。
面接で大事なことは、志望動機を熱意を込めて明確に伝えることができるかです。
ただ、「この大学に入りたい」ということを淡々と話しても、相手には伝わりません。
また、どんなにわかりやすく論理的な説明であっても、熱意や気持ちがこもっていなければ相手の心に響きません。
面接では論理的かつ情熱的なことが求められるのです。
ということは、論理的に話すことが苦手な人や、気持ちを込めて相手に伝えることが苦手な人にとって、面接は不利です。
実際、大学に入りたいという気持ちがちゃんとあるのに、熱意を上手く表に出せず、挙動不審な受け答えになってしまう人はとてもたくさんいます。
私の経験上、面接での受け答えについては練習である程度修正できますが、それでも面接が苦手な人は苦戦しやすく、合否の結果にマイナスに影響することも多々ありました。
公募推薦を受けるにあたり、あなたが面接向きかどうかは重要な要素です。

やはり明るくてコミュ力がありそうな学生が有利か…
(3)小論文の内容
公募推薦のうち、書類選考・小論文重視型の場合は、小論文の作成能力が問われます。
小論文では、基本的に短くとも1000字以上が必要ですから、文章を書き慣れていない人がこのような長文を書くと、文頭と文末で述べていることが変わってしまう一貫性のない文章になりがちです。
文章の型をマスターし、何度も練習を繰り返すことで長文を書く能力を手に入れましょう。
また、課題文の読解能力も重要です。
せっかく自分の意見を論理的に述べる能力があっても、課題文の内容を取り違えてしまえば解答の方向がずれてしまい、低得点になってしまいます。
読解力と文章力を鍛えるために、日ごろから小論文の演習に取り組みましょう。

小論文は型を覚えるとスラスラ書けるようになります。練習あるのみです。
公募制一般推薦の流れ
(1)募集要項の配布:6月ころ
各大学で募集要項が作成・配布されます。
推薦入試を考えている学生は、すぐに進路指導室などで募集要項を手に入れましょう。
欲しい要項がなかった場合は、進路の先生に取り寄せてもらうか、自分で要項を取り寄せましょう。
(2)願書配布:8~9月
出願予定者に願書が配布されます。
このころまでには三者面談などでどの大学に出願したいかなどの情報は学校・家庭・本人で共有されているはずです。
公募であっても推薦であれば学校側の協力が不可欠です。
この時までに協力体制を確立させましょう。
【関連】資料請求キャンペーン
(3)出願:10月
出願にあたっては、願書の締め切り日の確認が最重要です。
- 「消印有効」なのか
- 「当日必着」なのか
当日必着なのを勘違いしていたため、慌てて遠方の大学に直接出しに行くなどということがないよう十分注意しましょう。
もちろん、出願書類に誤りがないかどうか、先生にしっかりチェックしてもらうことも必要です。
早め早めに行動しましょう。

期限までに余裕をもって提出しましょう。
(4)面接練習:各高校による
出願が確定し、試験が迫ってくると面接練習が始まります。
姿勢・入退室動作・志望動機・将来の目標など、予想される基本的な質問について受け答えをする練習です。
例年、答えになる文章を丸暗記して、面接中に必死に思い出そうとする学生がみられますが、完璧な解答が求められるわけではありません。
要点のみを覚え、相手に伝わるように丁寧に説明する練習を心掛けましょう。

自分の面接姿を撮影して見直してみましょう。自分の意外なクセに気づくはずです。
ちなみに、私は想像以上にまばたきをしている自分に衝撃を受けました。
(5)小論文対策
面接練習と同時並行、あるいは、それ以前から小論文の対策が行われます。
文章の書き方、小論文で問われる論題の研究、時事問題のチェックなど実は小論文対策は簡単ではありません。
できるなら、高校2年生の段階から学校の先生に相談し、小論文の書き方を身につけておきましょう。
ちなみに、小論文の書き方がわかっていると、大学入学後に課されるレポート試験でとても楽です。
大学生活でも役立つスキルなので、早めの対策をお勧めします。
(6)各大学による選考:10月~11月
いよいよ、推薦入試の本番です。
それまでの練習の成果をはっきりするため、冷静に頑張りましょう。
意外と大事なのは、当日の試験会場での振る舞いです。
ある学生が入試会場の講義室がわからず、通りかかった人に待合室を尋ねました。
質問された人は丁寧に会場を教えてくれました。
しばらくして、面接会場に入ると、道を尋ねた人が面接官の、しかも中央の席に座っていました。
後で知ったのですが、その学部の責任者で合否判定に重要な役割を果たしていた教授だったとのことです。
入試会場では知らないうちに面接官や関係者とすれ違っているかもしれません。
面接前にマイナスな印象を持たれることは不利な要素ですよね。
油断大敵です。
(7)合格発表:12月上旬
推薦入試の合格発表は年内です。
もし、不合格だった場合は一般入試に切り替えなければなりません。
ダメだった時のことも考えて、入念に準備しましょう。
公募推薦は評定基準さえ満たしていれば誰にでもチャンスがある入試制度です。
しかし、一般試験に比べるとかなり早めの準備が必要です。
高校2年生段階からしっかりと進路を考え、準備を進めておきましょう。

落ちた時のために受験勉強をしっかり続けておくと、切り替えもスムーズになります。
推薦の大前提、調査書・評定平均について
推薦入試では、調査書の内容が重視されます。
代表的な項目は、各教科の評定や出席日数、特別活動や部活動・ボランティア活動などです。
これらについては、3年間を通じて積み重ねていくものです。
直前に対策をすることは難しいので、高校1年生の段階から怠りなく頑張りましょう。
特に、定期テストと提出物、出席日数は努力次第で向上させやすいです。
後で後悔することがないよう、前もって点数をあげましょう。
小論文対策
小論文は、初心者にとってはなかなかハードルが高いものです。
なぜなら、普段は400字を越える文章を書く機会があまりないからです。
小論文は最低でも800~1200字であり、もっと多い字数を求められることも珍しくありません。
長い文章を論理的に書くためには、「文章のパターン」の習得と繰り返しの添削指導が必要です。
加えて、
- 課題文を正確に理解する読解力
- 読解した内容をもとに意見を書く文章構成能力
- 自分の意見を述べるために必要な前提となる知識
など、思いのほかたくさんの能力が必要です。
早めに対策するべきは次の項目です。
小論文を課す大学に出願しようと考えている場合、できるだけ早く担任の先生や国語の先生と相談し、早めの対策をしましょう。

文章を作成する場面は社会人になっても多いです。がんばって慣れましょう。
(1)速読・要約能力
文章を早く正確に理解し、かつ、コンパクトに要約する能力のことです。
課題文の理解なくして、自分の考えを主張することはできません。
ここで出題意図を読み違えたり、課題文の内容を正確に理解することができなければ、「採点対象外」の小論文になってしまうでしょう。
(2)文章構成能力
せっかく自分の頭の中で主張をまとめることができても、それを文章にしなければ採点してもらえません。
相手に伝わる文章を書くためには一定の論理パターンが必要です。
- 「結論→本論→まとめ」
- 「本論→結論→まとめ」
どのような形でも良いのですが、採点者が読んだ時に、意味が分かるように文章を構成する力が必要なのです。
(3)前提となる知識
例えば、課題文の内容が人命救助だったとして、論題が災害時の人命救助の在り方について意見を述べるものだったとします。
その時に、過去の災害の時にどうだったのか、課題は何だったかを知っているか否かでは説得力が変わってきます。
少なくとも、過去1年の主要なニュースや受験する学部・学科に関するニュースや基礎知識は知っておくべきでしょう。
面接対策
面接では、志望動機が最も大切です。
- どうして、ほかの大学ではなくこの大学に入りたいのか。
- 入った後には何をしたいのか。
- 卒業後にはどうしたいのか。
このあたりが最重要項目です。
大学側が単に学力が高い学生が欲しいのであれば、一般入試の難易度を上げればいいのです。
しかし、大学に入ってから自発的に研究し、将来にまでつなげようという熱意を持っている学生なのか否かは、学科試験で測ることができません。
面接官が受験生について知りたいのは、「入学後にどれだけ何を頑張りたいのか」です。
そのために必要な対策は以下の通りです。
(1)徹底した大学研究

この大学に入りたいんです!
こう言い切るためには、その大学でしかやっていない独自性を見つけることが必要です。
しかし、パンフレットを並べただけでは違いが分からないかもしれません。
そこで注目するべきは、各大学の教授(研究者)がいったい何を研究しているかです。
一般的に、大学は教養課程が終わったら各研究者が主宰するゼミに入って研究を深めます。
これだけを聞けば何の問題もありませんが、その大学にドイツ文学の研究者がいなければ、その志望動機を魅力的に思う研究者もいないということになりかねません。
教授やゼミの内容まで調べて、はじめて徹底した大学研究を行ったと言えます。

その大学・学部の特徴を調べまくりましょう。
(2)自分の言いたいことを矛盾なく伝える練習
志望動機を一生懸命に丸暗記する光景は、面接の風物詩といってもいいでしょう。
しかし、大学側の需要からすれば、このような光景はあまりありがたくないことかもしれません。
面接官側は、受験生たちが完ぺきな志望動機をいかにスラスラ言えるかを採点するわけではありません。
要点が誤っていなければ、多少の言い間違いは問題になりません。
それよりも、自分の発言が相手の質問によってぶれることなく一貫性を保っている方がよほど大事です。

ミスをしても、明るくハキハキと喋っていれば相手はそんなに気にならないものです。
(3)言葉に気持ちが乗っているかどうか
どんなに論理的で、わかりやすい志望動機であったとしても、無味乾燥なものであれば効果は半減以下です。
どうしても入りたいという気持ちを乗せることで、はじめて相手に熱意が伝わります。
公募推薦を受けるにあたっての注意事項
公募推薦は有力な選択肢ではありますが、指定校推薦とは違って確実に合格できる入試ではありません。
受けるにあたってはいくつかの注意事項があります。
(1)落ちてもいいように、複数の志望校・学部を検討する
公募推薦は合否に関して手ごたえを感じにくい試験です。
また、合否の基準もあいまいなことが多く、確実に受かったかどうかはわかりません。
そういった入試は、合格発表まで合否が読めないのです。
ならば、受かること前提ではなく、落ちること前提で動いておくべきでしょう。
具体的には、一般受験の準備をしましょう。
公募推薦の入試は10月から11月に実施、合否は11月から12月にかけて判明します。
その間は、徹底的に一般入試に備えて勉強を進めましょう。
また、推薦が駄目だった時に備えて第二志望・第三志望のパンフレットを取り寄せておきましょう。
よくあるのが、受かったつもりになってほかの大学を検討せず、落ちてから慌てるケースです。
公募推薦の合格率は高くないのですから、落ちた時に備えるのが現実的です。
【関連】資料請求キャンペーン
(2)落ちてもめげない
実は、これが一番大事かもしれません。
いくら頭の中では「公募推薦は落ちてもおかしくない」と思っていても、心の中では合格を強く期待しています。
不合格という現実が確定した時に、「もう一度頑張ろう!」と立て直すか、
「もうだめだ。どうしよう。」と落ち込むのでは、天と地ほどの差があります。
合否判定からセンター試験(共通テスト)まで長くても2か月です。
たった60日しかありません。
落ち込んでいる暇などないのです。
いかに早急に気持ちを立て直すかが大事です。
今はオンライン学習がおすすめ

自習で成績が伸びない!

決まった時間に塾に行くのが嫌だ。
という方は、ぜひオンライン学習を活用してみてください。
特に、『全統模試』で有名な河合塾の『河合塾ONE』はおすすめです。
河合塾ONEは、スキマ時間に自由に利用でき、しかもAIが生徒にもっとも合った教材を提案してくれます。もちろん、分からない問題を聞ける先生もちゃんといます。

正直、ただ塾に行っても成績は上がりづらいです。大事なことは問題集を2周以上解くなどの反復勉強です。
塾のメリットといえば自習室ですが、コロナ禍で利用を制限されているところが多いですので、
分からない問題を聞いたり、今後の勉強の方針を相談するためにオンライン学習を選ぶのは非常におすすめです。
無料でお試しできるので、ぜひ経験としてオンライン学習にも挑戦してみてください。
近年、入学試験の仕組みは大きく変化しています。
さらに、コロナ禍などの社会変化もとても大きく、中退を考えている大学生も多い昨今。
もしあなたが大学に行く意味について悩んでいるなら、ぜひこちらの記事も参考にしてみてください。