この記事を読むことで、「理系の学部・学科選びの具体的な方法」が分かります。
「理系選択で数学ⅢCまで勉強するし、理系基礎科目も全部カバーする。でも志望学部はまだ決まっていない。」
「理系選択で大学受験が近づいているけど、まだ行きたい学部・学科が決まっていない。焦る。」
という理系受験生はたくさんいます。

理系系を選択するぐらいなら、
『薬学を勉強したい』
『ロボット工学を学びたい』
とか、ある程度将来目指すものが決まっているんじゃないの?
と思われがちですが、意外と理系の中で行きたい学部が決まっていない学生は多いものです。
学部・学科選びに迷っている理系受験生たちは、ぜひこちらの記事を参考にしてください。

この記事の著者は、大学非常勤講師の「もんでん」さんです。
※志望校選びのために無料資料を入手しよう
大学の資料は信頼性が高く、研究や制度、設備内容が分かりやすく紹介されています。
志望校の資料が手元にあると勉強のやる気も上がりやすいので、早めに入手しておきましょう。
今の得意科目で専攻分野を決めない

こんな言葉を耳にしたことはありませんか?
- 化学が得意だったら、生物学科へ
- 物理が得意だったら、化学科へ
- 数学が得意だったら、物理学科へ
これは理学部での学科選択を表した言葉です。
大学に入ると、
- 生物学科では、より細胞レベル遺伝子レベルなどを「化学反応」で理解します。
- 化学科では、化学反応の過程をエネルギーや電子などの「物理」の言葉を使って理解します。
- 物理学科では、公式の解説ではなく「数学」を使って公式の導出を行うことで理解を深めます。
- 地学科では、これら「物理・化学・生物」すべての知識が必要になります。
つまり、大学受験で得意な科目から安易に将来の専攻分野を決めると、
入学後に「自分にしっくりこない!」と後悔してしまうことがあるのです。
「化学が得意!」「生物が得意!」と自信のある科目があるのは良いことですが、それはあくまでも大学受験での話です。
自分の将来を左右する学部・学科選びでは、「今の得意科目」よりも「自分の興味がある分野」を選びましょう。

”好き”が先に来て、そこを目指す手段として勉強するわけですね。
「物理が嫌い」で専攻分野を決めない
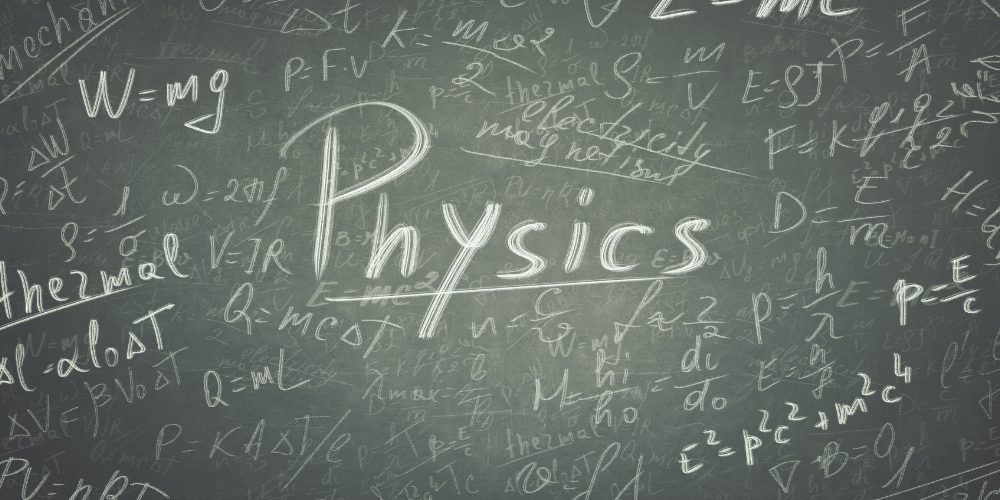
特に、「物理が嫌い」で専攻分野を決めるのは辞めましょう。
医学部、薬学部、歯学部を狙っている受験生なら、諦めて物理をしっかり勉強すると思いますが、
たとえば「生物関係で進学しようとする受験生は、だいたい物理が嫌い」です。
しかし、大学の生物学部では基本的に物理学概論は必修ですし、農学部でも物理が必修になっている大学があります。
入試で物理から逃げられても、理系学部に進学すると物理から逃げられないことがよくあるのです。
物理が嫌いだからと「物理と関わりが無さそうな学部」を目指すのではなく、
しっかり学部・学科についてリサーチした上で進路を決めましょう。
ちなみに、数学が得意なのではなく「大好き」なら、数学科をおすすめします。

結局、数学や英語は大学入学後に勉強する必要がありますから、受験時にがんばって勉強しておけば、大学生になってから楽になるはずです。
学科・研究室の具体的な研究内容が大事

それぞれの学科・研究室が具体的にどんな研究をしているのか、しっかり調べておきましょう。
これを怠ると、入学後にとんでもなく後悔してしまう可能性があります。
自分が志望する専攻分野が決まっていない段階でも、少しでも興味がある分野で
- どんな先生が何の研究をしているのか
- どんな科目(授業)があるのか
をHPの「シラバス」や研究室紹介で調べてみましょう。
大雑把に調べるのではなく、研究内容・授業内容について詳細に調べることが重要です。
研究内容のリサーチはとても大切
具体的な研究内容までしっかり把握して学部・学科選びをしておかないと、

志望校に合格したけど、いざ進学してみると大っ嫌いなゴキブリの研究をさせられた!
などのように予想外なことも起こりえます。
ちなみに、これは実話です。
朝から晩まで、大嫌いなゴキブリの解剖をさせられた学生だっているのです。
入学後に後悔しないよう、理系の学部・学科は徹底的にリサーチしましょう。

大学は学生もそれぞれ「専門的な分野」を研究しますから、勘違いであなたの興味がない分野へ進むと地獄です。
授業内容はシラバスを調べよう

それぞれの大学の授業内容の詳細は、各大学のシラバス(授業計画書)で確認することができます。
近頃、ほとんどの大学が授業内容をHP上でシラバスとして公開しています。
ぜひ、「○○大学 □□学部 シラバス」で検索してみてください。
単に授業名が「生物学概説」と書いてあっても、シラバスを細かく見てみると、
- 器官の再生メカニズム
- 生物の大きさを決める分子メカニズム
- 遺伝子の発現
などのように、実は授業内容がとても具体的であることが多々あります。
そして、この授業内容が自分のまったく興味がない分野だと、入学後にとても後悔してしまいます。
表向きの名称に惑わされることなく、志望校の具体的な授業内容・研究内容に注目しましょう。
理学部と工学部の違いとは


理学部と工学部の違いが分からない。
という受験生は、理系選択の中にも意外とたくさんいます。
そんな受験生たちのために、理学部と工学部の違いを簡単に説明すると以下のようになります。
●「何にでも応用可能な原理を研究するのが理学部」
●「それを使って新しい何かを作り上げるのが工学部」
「ものづくり」には、以下のように2段階あるということですね。
①原理を研究する(理学部イメージ)
②原理を利用して実用化・既存技術を発展させる(工学部イメージ)
どちらも密接に関わり合っているので、
「片方を専攻すれば、もう片方は勉強しなくていい」というわけではありません。
しかし、「自分はどちら側をメインに携わりたいのか」と考えておくことはとても重要です。
ものづくりに興味がある方は、理学部と工学部のどちらをメインで志望するのか考えましょう。

「ものづくり」の川上寄りは理学部、川下寄りは工学部というイメージですね。
【1】理学部に向いている学生とは

理学部には、今は決して何の役に立つかわからないものでも、重箱の隅をつつくように一生懸命に研究を続け、
自分でも

これ、何の役に立つんじゃろう?
と自問自答を繰り返しながら研究している学生や研究者がいっぱいいます。
しかし、理学部がとても重要な学部のひとつであることは間違いありません。
少し専門的な話になりますが、例えば「電子は特殊な環境では双子で現れる」ことがあります。
この「双子の電子」はアインシュタインが初めて提案しました。
そして、その性質を今に至るまで一生懸命研究していると、現在のコンピュータを越える速度のコンピュータを開発できることが分かってきました。
いわゆる「量子コンピュータ」と呼ばれるものですが、もしこのコンピュータが実用化されればものすごい技術革新が起きます。
一例を挙げると、量子コンピュータで設定されたパスワードの組合せは、
文字通り「天文学的数字」に変換され、
現代のコンピュータでセキュリティを突破するのは至難になるとされています。
当然、計算速度も桁違いに向上します。
このように100年以上前のアイデアが現在やっと実用化され、最先端のコンピュータが作られようとしているのです。

コンピューターサイエンスを学ぶなら工学部でしょ!
と考えている方は多いかも知れませんが、
コンピューターサイエンスの分野を発展させる大元には、実は理学部の研究成果があるというわけです。
原理が分からないと応用することはできませんし、ましてや原理を利用して開発・実用化することもできません。
そして、「技術」は日々更新されていきますが「原理」は古くなりません。
原理の段階から「ものづくり」に関わりたい方は、理学部を進路として考えてみましょう。

実用的なものを作ることだけでは人類は発展できません。大元の理論を作ることも重要だということですね。
【2】工学部に向いている学生とは
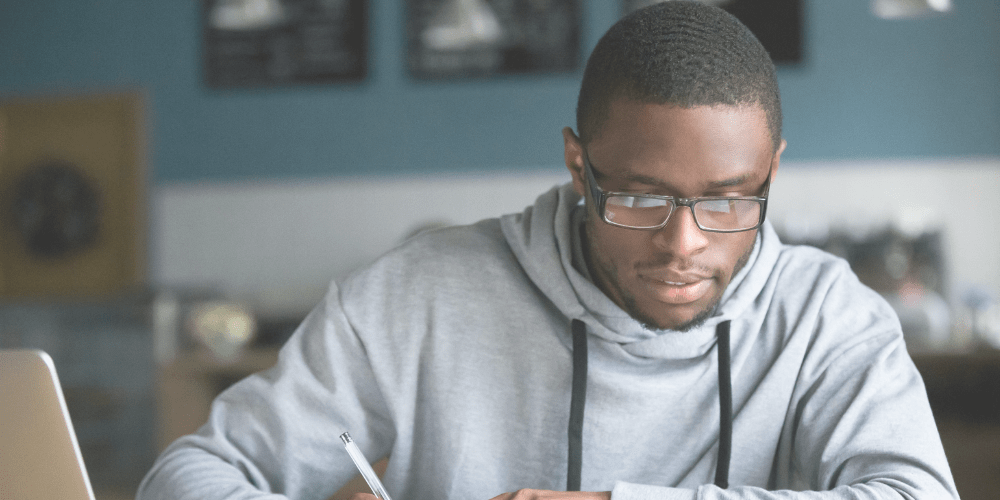
工学を机上で勉強しただけでは、工学部生はつとまりません。
図面を引いたり、部品加工の技術を磨くために実際に工場で実習したり、工学部には「手作業・工作」がとても重要です。
理学部でも実験、実習やフィールドワークがありますが、
理学部は”誰でも出来る”実験指導書があり、それに従って実験してレポートをしっかり書けば単位はまず出ます。
一方、工学部では
- 「図面を引く」
- 「部品加工する」
- 「器用さが必要な実験」
など、決定的に手作業が関わってきます。
こういった手作業にあまり苦を感じず、むしろ楽しめる受験生には工学部が向いていると言えます。
例えば、工学部の建築学科に進めば、はじめは耐久計算など理論を中心に勉強しますが、学年が上がると実際に図面を引きます。
さらに、その図面を元にして紙とはさみを使い、プレゼン用の完成予想建築物(Ⅰ/20スケールなど)を工作する実習がたくさん入ります。
このような工作実習は膨大な時間を消費しますから、大学生活がとても忙しくなります。
自分の手で何かを作るのが好きなのか、それとも理論を研究するのが好きなのか、しっかり考えましょう。

”カタチ”あるものを作りたいなら、工学部が向いているかもしれません。
学部・学科のイメージだけで進路を決めない

学部・学科のイメージだけで進路を決めるのは辞めましょう。
例として、

農学部には行きたくない。
と考えている薬学部志望の受験生の場合を挙げます。
農学部に「農業」というイメージが強く付いていて、「畜産」「キノコを育てる」など、

農学部は卒業後に農業をする人が行くところでしょ?
と思っている方は意外と多いです。
しかし、このようなイメージで誤解をしていると、自分の可能性を狭めてしまう恐れがあります。
「本当は薬学部に行きたいけど、私のいまの学力的に薬学部進学が厳しいんです。」
という方、そんな方々の中には農学部ととても相性が良い学生がいるんです。
薬学部に行きたい理由は、薬学部志望の受験生によってそれぞれ異なります。
具体的には、以下のような理由で薬学部を目指している理由を分けることができます。
- 「薬剤師になりたいから、薬学部に行きたい」
- 「研究者として製薬会社に勤めたいから、薬学部に行きたい」
もし、薬剤師になりたいのであれば、薬学部の方が「国家試験突破!」を目標としたカリキュラムを組んでいるのでおすすめします。
しかし、研究者として製薬会社に勤めたいのであれば、「理学部生物学科」や「農学部」でも目標を達成できる可能性が高いです。

研究分野は同じでも、働き方や必要な資格は業種によって大きく異なります。
農学部でも、「ゲノム創薬」などに必要な基礎的な単位を取ることは可能です。
「6年制の薬学部に4年次に編入学する」という迂回路の選択も視野に入れることができます。
現在、農学部はバイオテクノロジーの先端を走っています。
大学にもよりますが、理学部生物学科と農学部の明確な境界線は無くなってきていて、両学部ともにゲノムレベルの研究開発・応用が盛んです。

薬学に関わる研究がしたいから、薬学部に行かなきゃ!
とイメージだけで視野を狭める必要はないのです。
学部・学科のイメージだけで進路を決めるのではなく、自分の目的から逆算して学部・学科を選びましょう。
ただし、農学部は環境問題とも密接に関係している学部です。
農学部4年生になると、「発生学・免疫学」といった理系テーマだけでなく、「環境経済・食糧問題」といった文系色のあるテーマや科目も増えます。
これらもとても重要なテーマですが、理系肌の学生の中には

文系チックなテーマは自分に合っていない。
と感じる学生も多いと聞きます。
農学部志望の受験生は、志望校選びの際にシラバスで授業内容をしっかり確認しておきましょう。
受験時に理系の学部選びができない場合

どうしても志望学部を決められない受験生のために、
現在では、いわゆる「学部・学科は大学に入ってから決めてね」学部があります。
どこの大学も研究機関という位置づけを持っていますから、弟子を育てるのは大学の使命です。
ですので、以前まではどの大学も学生が1年生の時から基礎を叩き込み、自前の弟子を育てて研究者にするためのシステムを主に運用してきたわけです。
ところが、最近は入学後に進路に迷い、

転学・転学科させてください。
という希望を出す学生が後を絶ちません。
そのため、こういった学生のために「入学と同時に学部・学科を決めなくてもいい」という制度を作った大学が増え始めました。
さすがに学部横断できるものは少ないですが、せめて学部内であれば、例えば「2年生になるまでに学科を決めましょう」というシステムを用意しているのです。
東大の教養学部をはじめ、京大、名古屋大、阪大、東北大と広大、北海道大、筑波大などがそのようなシステムを取っていることは有名ですね。
さらに、地方国公立大学(新潟大学新理学部、静岡大学理学部、愛媛大学理学部の一部)でも採用されはじめていますので、気になる方は探してみましょう。

受験時に、自分の専門分野を明確にイメージするのはとても難しいですし、実際に研究に触れてみると気が変わることもあります。
「とにかく理系には進みたい」と漠然と考えているなら、上記のような学部・大学を参考にしてみましょう。
また、多くの大学では、所定の用件をクリアすれば、転学科・転学部を認めてくれるシステムを用意しています。
※埼玉大学のように、HP上ででおおっぴらに転学部学科マニュアルを公開している大学もあります。
志望する理系学部は慎重に選ぶ

行きたい学部・学科が明確に決まっていない時は、それぞれの大学のフォロー体制を調べた上で進路を決めるといいでしょう。
大学選びで迷うのも受験生の特権です。

進路選びは辛いですが、きっと楽しさも感じるはずです。
理系だけど行きたい学部・学科が明確に決まっていないという方は、入学後に後悔しないよう、徹底的にリサーチしましょう。

